あなたのまちにも自主防災組織を
1.自主防災組織とは
大きな災害が発生したとき、被害を最小限に抑えるためには、自分自身を守る「自助」、隣近所の相互連携による「共助」、消防などの公共機関による救助・支援などの「公助」がそれぞれ最大限に機能を発揮することが重要です。そのなかでも、自主防災組織は「共助」の主体であり、連合町内会や通学区など生活環境を共有している地域で住民の手による自主的な組織を基本とするものです。
【参考】災害対策基本法第7条第3項
住民は、「自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等防災に寄与するように努めなければならない」こととされています。
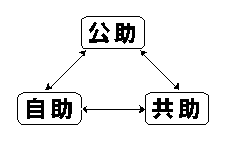
2.自主防災組織の必要性
大地震などの災害の場合、建物の倒壊や火災など、個人では対応が困難な事態が同時に広い範囲で発生することが予想されます。また、これらの被害や道路交通網の破壊、電話の不通や電気・ガス・水道施設などが寸断されることなどにより、発生直後は、一時的に消防など公共機関の対応能力を超える状況におちいる恐れがあります。
このため、特に災害の発生直後においては、地域の皆様がお互いに協力し「自分たちの地域は、自分たちで守る」ことが大変重要となります。
3.自主防災組織の効果
大きな災害が発生した際には、地域の皆様がお互いに助け合う「共助」により、被災者の救出・救助、初期消火活動、避難活動や安否確認などの自主防災活動が素早く・効果的に行われる必要があります。自主防災活動を行う地域住民が災害後のパニックを引きずり、各自バラバラに行動していても効果は低く、かえって混乱を招くおそれすらあります。地域としての防災力を最大限に発揮するために、地域住民相互の共通認識に基づく組織的な活動が必要となります。
地域としてまとまり、災害時の組織的な活動を行うために、地域住民等による自主防災組織の設置・運営が必要となります。
自主防災組織においては、平常時には、災害が起こったときに予想される被害をできるだけ抑え、地域防災力が最大限発揮できるような体制・状態を準備し、そして災害時には、その状況に応じて、初期消火、救出・救護、避難誘導などの災害対策を迅速に行います。
4.自主防災組織のつくり方
自主防災組織の要件
自主防災組織は、地域の住民が組織結成に合意し、規約、組織、活動内容を定めることで成立します。市や消防に許可申請などの手続きを行う必要はありません。しかし、防止活動を行うには、市や消防機関との連携が必要なため、市や消防署に組織の結成を知らせておくことは必要です。
適正な組織の規模
また、自主防災組織は、地理的条件、生活環境などから見て、地域として一体性を有する大きさが最も効果的に活動できる規模とされています。そのため、自主防災組織の多くは、連合町内会や小学校の通学区域などを目安に結成されています。
班編制例
会長・副会長・役員(統括・活動計画)
- 消火・救出班
- 避難班
- 情報収集・伝達班
- 物資・給食班
- 要援護者支援班
規約で定める項目例
- 組織の名称・目的
- 事業内容
- 役員の選任・任期
- 会議(総会、役員会)
- 組織表、会員
- 経費に関すること
- その他必要事項
【word版】設立報告 (Wordファイル: 31.5KB)
【word版】防災計画 (Wordファイル: 24.5KB)
【word版】組織図 (Excelファイル: 17.8KB)
設立の手順
- 自治会、地域の既成組織、地元消防団、防災に関心のある方と連携を図りながら、設立の合意をとる。
- 自主防災会の規約、役員名簿の作成
- 市災害対策課へ届け出
地域安全安心コミュニティ
特に大きな災害が発生した場合は、地域の力を総動員して立ち向かうことになります。お年寄りや障害を持った方、小さいお子さんなど、いわゆる災害時要援護者の緊急避難には、地域の民生委員や福祉団体などの協力が欠かせません。また、救助・救護のためには地元消防団、医療機関、事業所などとの連携が大変効果を発揮します。長期に避難所を開設することになれば、心のケアや秩序維持などのため女性団体や防犯委員、災害ボランティアといった方々の協力があれば心強いものです。
組織化にあたっては、地元消防団、婦人消防クラブ、防犯協会支部、交通安全協会支部、民生委員、児童委員、学校PTAなど地域の力を最大限に活かしましょう。
そして、組織の活動範囲を防災だけに限定せず、安全で安心して住める地域づくりのための土台とすることは、失われがちな地域コミュニティの醸成にも役割を果たす効果が期待できます。
5.地域防災力向上のために
地域の防災は、まず、どのような災害が地域に被害を及ぼすかを知ることから始め、そして、それらの災害に対する弱さを認識し、その上でいざ災害が起きても致命的な被害に至らないように準備をしていきます。
しかし、これらの実現には時間やお金、労力がかかることでもあり、必要なことを一度にやることは困難です。まず実現可能な目標を定め、年次計画などにより、段階的に無理なくそして着実に地域防災力の向上を進めて行きます。
そして、組織の規約などにより、係りの方の負担にならない範囲で役割や仕組みを明確にし、定期的に自己点検を行いながら自主防災活動を継続していくことがもっとも大切なことなのです。
6.自主防災組織の活動
自主防災組織が行う防災活動の主なものが防災訓練です。
- 情報収集・伝達訓練
地域内の被災状況や避難の状況などの情報を正確かつ迅速に収集し、地域住民や消防等関係機関と共有する。 - 消火訓練
消火器や可搬式小型動力ポンプなどの消火用資機材の使用方法および消火技術を習熟する。 - 救出・救護訓練
救出用資機材の使用方法や負傷者等の応急手当の方法、救護所への連絡、搬送の方法などについて習熟する。 - 避難訓練
避難の要領を把握し、定められた避難所まで迅速かつ安全に避難できるようにする。 - 給食・給水訓練
限られた資機材を有効に活用して食糧や飲料水を確保する方法、技術を習熟する。


7. 八戸市自主防災組織育成事業
東日本大震災からの復興と災害に強いまちづくりを目指し、自主防災組織が行う防災資機材の整備を支援するため、「八戸市自主防災組織育成事業」を創設しました。
8.自主防災組織の結成・活動を支援しています
市では、自主防災組織の設立を支援するため、連合町内会などへの説明会の実施、規約作りや地域での防災訓練実施に関するお手伝いをしています。
詳しくは、災害対策課(内線2516)または最寄りの消防署へお問い合わせください。
また、自主防災組織の活動に要する経費の一部を支援するため、「自主防災組織活動支援助成金」を創設しました。
9.八戸市自主防災会連絡協議会
平成27年3月30日、『八戸市自主防災会連絡協議会』が発足しました。
設立の目的
自主防災会相互の連携を密にし、自主防災体制を充実・強化し、地域防災力の向上を図ることを目的としております。
自主防災だより
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理部 災害対策課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
地域防災グループ 電話:0178-43-9225/0178-43-9564 ファックス:0178-45-0099













更新日:2024年03月22日