八戸南部氏庭園
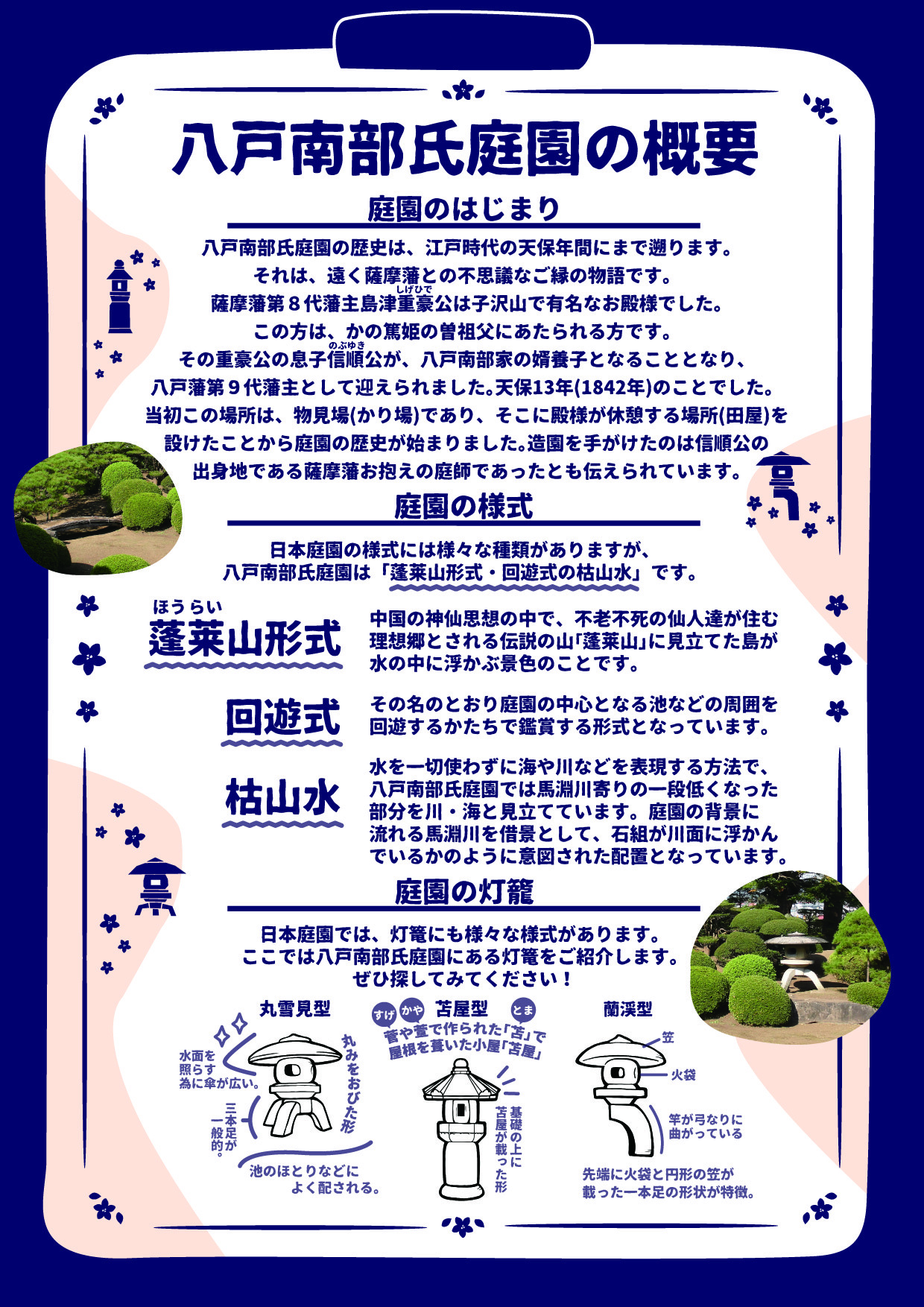
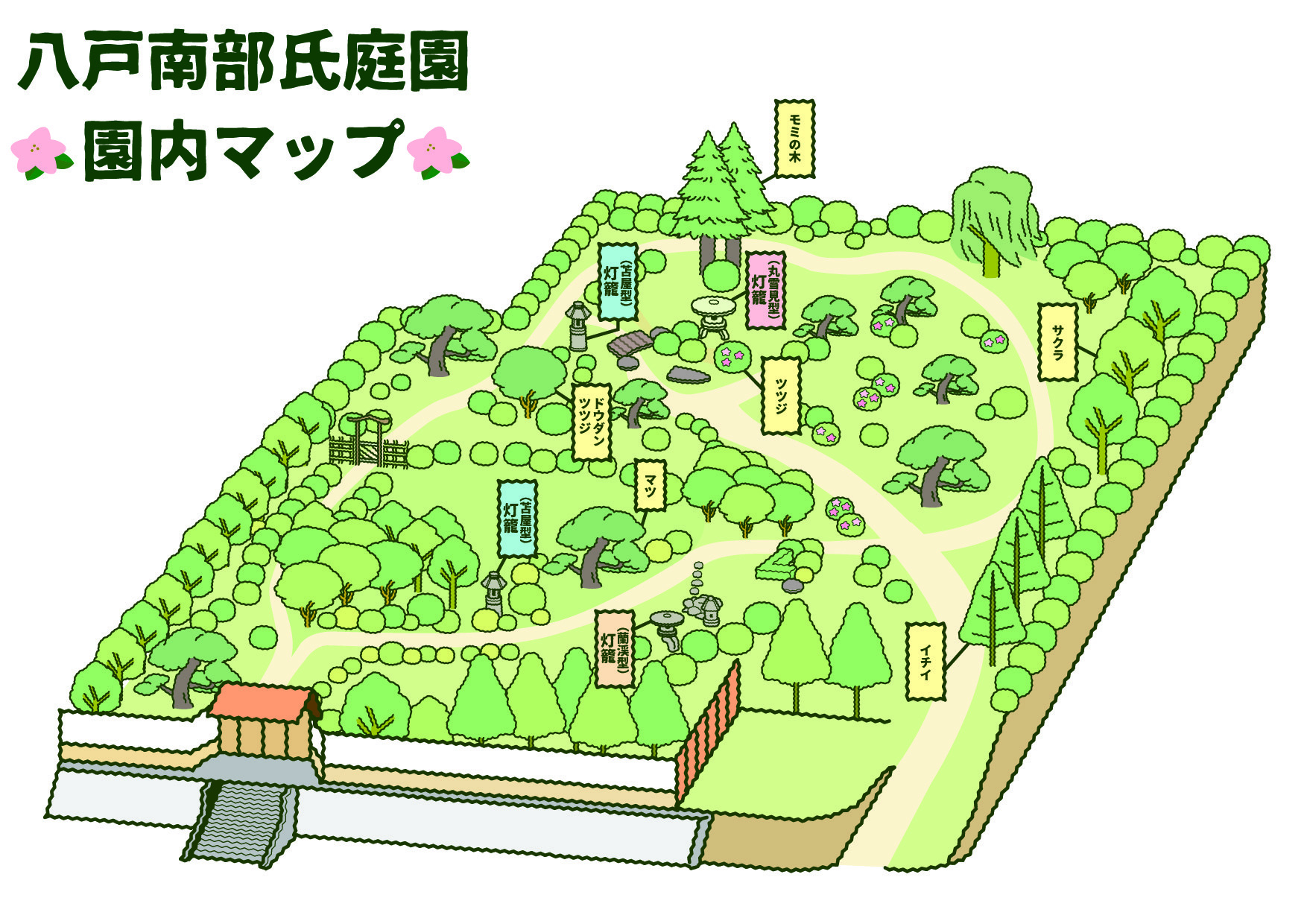
春・秋の開園について
八戸市南部氏庭園は例年、ツツジが咲く春(5月中旬~下旬頃)と紅葉の秋(10月下旬~11月上旬頃)の年2回、無料で一般公開を行っています。
令和7年度の開園日程と概要については、以下のとおりです。
秋の開園
開園期間
令和7年11月6日(木曜日)から11月13日(木曜日)まで(8日間)
10時00分から15時00分まで
(注意)開園時間は16時00分ではなく15時00分までです!
 |
 |
 |
庭園内のボランティアガイド
11月7日(金曜日)から11月10日(月曜日)まで(4日間)
10時00分から15時00分まで
チラシ
秋の開園のチラシはこちら(PDFファイル:3.2MB)
春の開園 (注意)開園期間は終了いたしました。
開園期間
令和7年5月15日(木曜日)から5月22日(木曜日)まで(8日間)
10時00分から16時00分まで
 |
 |
 |
庭園内のボランティアガイド
5月16日(金曜日)から5月19日(月曜日)まで(4日間)
10時00分から16時00分まで
チラシ
春の開園のチラシはこちら(PDFファイル:403.7KB)
その他
YouTubeの各チャンネルに八戸南部氏庭園開園時の様子を紹介する動画が掲載されております。以下のリンクからどうぞご覧ください。
- 八戸トピックス Hachinohe Cable Television カルチャースポットはちのへ #18 南部氏庭園【八戸市の文化公共施設をご紹介】
- 八戸市広報チャンネル【八戸市】八戸南部氏庭園〜春の開園〜
(注意)管理の都合上、開園期間以外は八戸南部氏庭園の一般公開を行っておりませんのでご了承ください。
交通案内について
所在地
八戸市売市四丁目23-3ほか

バスをご利用の場合
- 八戸市中心街バスターミナル「六日町」のりばから、市営バス「多賀台団地」行き(片道190円)、南部バス「五戸」行き(片道190円)または八食200円以下バス(片道170円)のいずれかに乗車
- 「緑ヶ丘」で降車し、大橋方面へ進み、熊野堂交差点を渡る
JR八戸線をご利用の場合
- JR八戸線「長苗代駅」で降車
- 「長苗代」バス停から、市営バス「中心街」行き(片道190円)、八食200円以下バス(片道170円)または十和田観光電鉄十和田八戸線(片道190円)のいずれかに乗車
- 「緑ヶ丘」バス停で降車し、大橋方面へ進み、熊野堂交差点を渡る
自家用車をご利用の場合
国道45号(青森・十和田方面)からの場合
- 国道45号の北バイパスを南下
- 下長交差点を右折
- 馬淵川を越え、「南部氏庭園」の看板左折
八戸自動車道をご利用の場合
- 八戸インター(三沢・十和田・フェリー埠頭方面)
- 県道29号
- 松園町交差点右折
- 国道104号
- 博物館入口交差点左折
- 熊野堂交差点直進
(注意)駐車場に限りがありますので、来園にはなるべく公共交通機関をご利用ください。
(注意)開園期間中は案内看板を設置しています。
この記事に関するお問い合わせ先
観光文化スポーツ部 文化創造推進課 文化創造グループ
〒031-0031 青森県八戸市大字番町10-4 八戸市美術館内
電話:0178-43-9156 ファックス:0178-38-0107
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-













更新日:2025年10月10日