杤内 吉忠
杤内 吉忠(とちない よしただ)
文政8年(1825年)~明治26年(1893年)
-変革期を支えた教育者-
上り街道のお茶番を代々務めた杤内家の長男として生まれる。藩士の蛇口胤年から易学を、名僧瓦鏡(がきょう)から仏学を学び、嘉永3年(1850年)山伏小路に私塾を開く。藩校である文武講習所の儒学小教授だったこともあり、私塾は盛況を極め、山下(やまのした)組や杤内党と呼ばれ強い影響力を持っていた。
安政4年(1857年)、対外危機の高まりから江戸へ出て、砲術や西洋の兵隊訓練術を学ぶ。大砲の発射実験で重傷を負いながらも、7年(1860年)には八戸藩西洋鉄砲隊と槍剣の師範に命じられ、維新の動乱期に藩政を支えた。
一方、板橋山と蒼前平の開墾、養蚕技術の導入など、産業の振興にも力を尽くす。維新後は八戸小学の取締役兼小教授などを務めたが、明治10年(1877年)に隠居し、名久井山麓の葉柴山に帰農する。しかし、八戸の近代化に邁進する青年指導者北村益の求めに応じ下山、20年(1887年)、八戸初の地方劇場である山伏小路の於多福座(おたふくざ)に明義会を組織した。
ここから、大沢多門、山内光武など多くの指導者を輩出する。杤内は、幕末から明治の変革期に、私塾を開いて若者を教育し、次代を担う数多くのリーダーを育て、八戸における維新を支えたのである。

栃内の塾があった現在の山伏小路

明治22年(1899年)北村益は明義会を引き継ぎ八戸青年会を立ち上げ、八戸の近代化を推進する胎動となった。(写真は八戸青年会の農園 八戸市立図書館蔵)
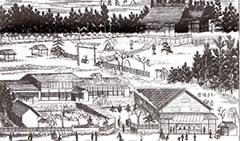
大沢多門が旧藩学校を利用して明治5年(1872年)に創設した於多福座(図は明治26年(1893年)に新築した後のもの 八戸市立図書館蔵)













更新日:2021年03月11日